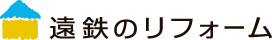リフォーム研究室
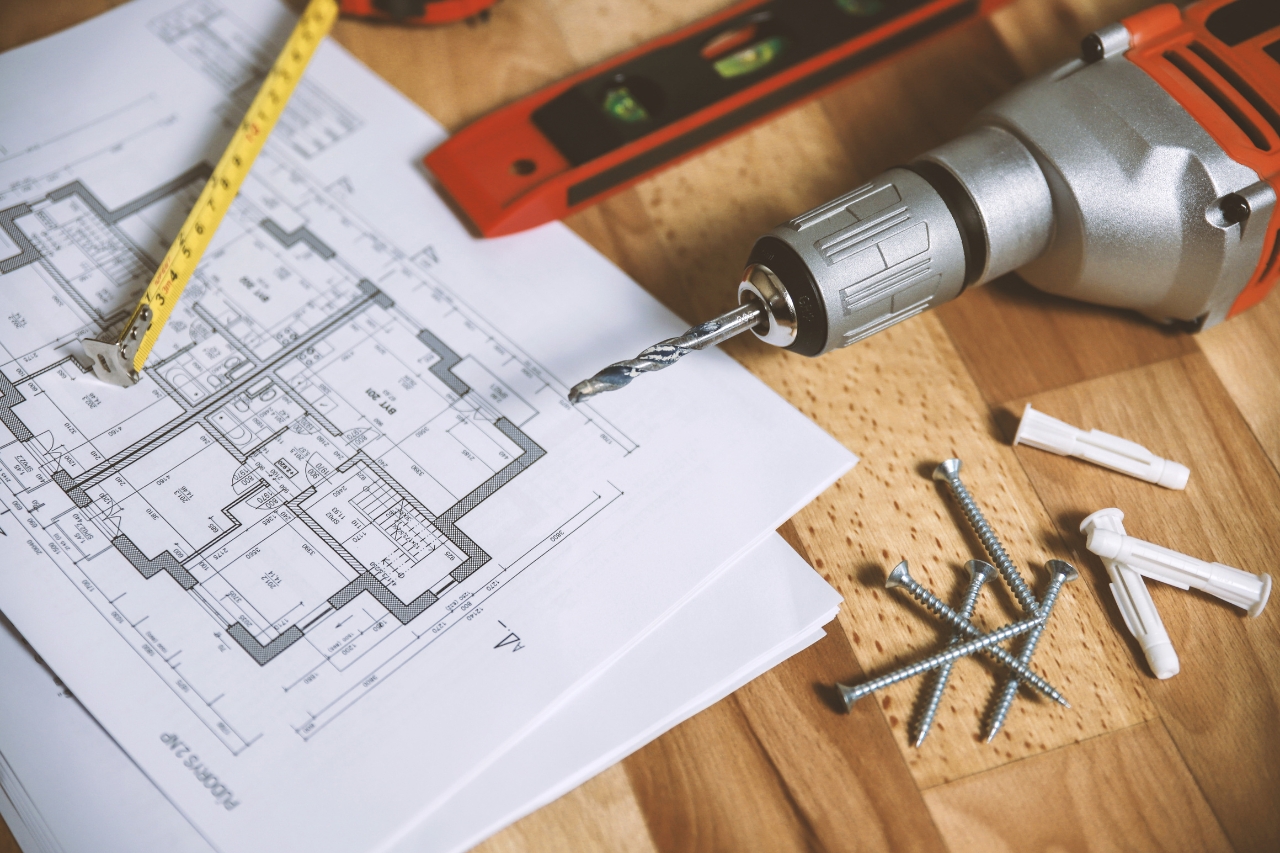
建物を新築したりリフォームを行ったりする際は、建築確認申請が必要になるケースがあります。建築確認申請は、安全で安心な住まいづくりに欠かせない重要な手続きです。
しかし、リフォームにおいては、建築確認申請が必要な場合と不要な場合があります。そこでこの記事では、建築確認申請が必要なケースや、リフォーム時に気をつけるポイントを解説します。
しかし、リフォームにおいては、建築確認申請が必要な場合と不要な場合があります。そこでこの記事では、建築確認申請が必要なケースや、リフォーム時に気をつけるポイントを解説します。
建築確認申請とは?

建築確認申請とは、建築基準法第6条に基づき、建物が安全性や耐震性、防火性などの基準を満たしているかを確認するための手続きです。
建築確認申請は違法建築物の建築を防ぐことを目的としており、建物の安全性と周辺環境への配慮を確保するために行われます。建築確認申請が通ることで、建物の設計・構造計画が法律に適合したものと認められ、工事を始めることができます。
家を新築する際には必ず建築確認申請が必要です。また、リフォームでも工事内容や条件によっては、建築確認申請が必要となる場合があります。
建築確認申請は違法建築物の建築を防ぐことを目的としており、建物の安全性と周辺環境への配慮を確保するために行われます。建築確認申請が通ることで、建物の設計・構造計画が法律に適合したものと認められ、工事を始めることができます。
家を新築する際には必ず建築確認申請が必要です。また、リフォームでも工事内容や条件によっては、建築確認申請が必要となる場合があります。
リフォームで建築確認申請が必要なケース

リフォームでも、以下のようなケースは建築確認申請が必要になる場合があります。
・10㎡を超える増築
・防火・準防火地域での増築
・鉄骨2階建て以上、木造3階建て以上の建物での大規模な修繕・模様替え
「大規模な修繕・模様替え」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の修繕・模様替えです。
具体的には、下地工事を伴う屋根の葺き替えや外壁全体の改修、スケルトンリフォーム、間取り変更などが含まれます。
上記は2024年現在の基準です。2025年4月に施行が予定されている建築基準法の改正により、リフォームでの建築確認申請が必要となるケースが増加すると考えられています。
・10㎡を超える増築
・防火・準防火地域での増築
・鉄骨2階建て以上、木造3階建て以上の建物での大規模な修繕・模様替え
「大規模な修繕・模様替え」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の修繕・模様替えです。
具体的には、下地工事を伴う屋根の葺き替えや外壁全体の改修、スケルトンリフォーム、間取り変更などが含まれます。
上記は2024年現在の基準です。2025年4月に施行が予定されている建築基準法の改正により、リフォームでの建築確認申請が必要となるケースが増加すると考えられています。
2025年法改正の概要と4号特例廃止の影響

2025年4月施行予定の建築基準法の改正は、リフォーム時の建築確認申請に大きな影響を与えるといわれています。
この法改正の一環として「4号特例」の廃止が決定されており、小規模建築物でも建築確認申請が必要になるケースが増える点に注意が必要です。
この法改正の一環として「4号特例」の廃止が決定されており、小規模建築物でも建築確認申請が必要になるケースが増える点に注意が必要です。
4号特例とは?
4号特例とは、建築基準法の「建築基準法第6条の4」に基づく特例措置のことで、4号建築物に対する審査省略制度のことです。4号特例は、一定規模以下の小規模建築物(4号建築物)に対して、一定の条件を満たした場合に一部の審査や検査が免除される制度です。
2024年現在、住宅は「2・3・4号建築物」の3タイプに分類されており、日本では「4号建築物」に該当する住宅が一般的です。
・2号建築物:木造3階建て以上の建物
・3号建築物:鉄骨造・RC造など(木造以外)で2階建て以上の建物
・4号建築物:木造2階建て以下、または平屋の一般的な住宅
2024年現在は、4号建築物に該当する住宅では、増築以外のリフォームでの建築確認が不要(建築確認における構造審査を省略可能)となっています。
2024年現在、住宅は「2・3・4号建築物」の3タイプに分類されており、日本では「4号建築物」に該当する住宅が一般的です。
・2号建築物:木造3階建て以上の建物
・3号建築物:鉄骨造・RC造など(木造以外)で2階建て以上の建物
・4号建築物:木造2階建て以下、または平屋の一般的な住宅
2024年現在は、4号建築物に該当する住宅では、増築以外のリフォームでの建築確認が不要(建築確認における構造審査を省略可能)となっています。
4号特例廃止による影響
2025年4月から施行予定の建築基準法改正により、従来の「4号建築物」という分類は廃止され、従来の4号建築物に該当していた小規模な住宅は「新2号建築物」または「新3号建築物」に再分類されます。
・新2号建築物:木造2階建て、および延べ面積200㎡を超える木造平屋
・新3号建築物:延べ面積200㎡以下の木造平屋
この改正により、一般的な住宅に対しても、建築確認申請の対象範囲が変更されます。
具体的には、新2号建築物に該当する住宅は、すべての地域において増築だけではなく、屋根の葺き替えや外壁全体の改修、スケルトンリフォーム、間取り変更などの「大規模な修繕・模様替え」でも建築確認申請が必要になります。
ただし、新3号建築物に該当する住宅では「大規模な修繕・模様替え」での建築確認申請は不要です。
4号特例の廃止により、リフォームにおいては建築確認申請の手続きなどが増えるとされますが、その一方で安全基準がさらに強化されるともいえます。
・新2号建築物:木造2階建て、および延べ面積200㎡を超える木造平屋
・新3号建築物:延べ面積200㎡以下の木造平屋
この改正により、一般的な住宅に対しても、建築確認申請の対象範囲が変更されます。
具体的には、新2号建築物に該当する住宅は、すべての地域において増築だけではなく、屋根の葺き替えや外壁全体の改修、スケルトンリフォーム、間取り変更などの「大規模な修繕・模様替え」でも建築確認申請が必要になります。
ただし、新3号建築物に該当する住宅では「大規模な修繕・模様替え」での建築確認申請は不要です。
4号特例の廃止により、リフォームにおいては建築確認申請の手続きなどが増えるとされますが、その一方で安全基準がさらに強化されるともいえます。
リフォームにおける建築確認申請の流れ

建築確認申請の依頼者はリフォーム工事の施主ですが、実際の申請対応はリフォーム会社が代行するのが一般的です。しかし、ご自身で建築確認申請の流れを把握しておくことも重要です。
ここでは、リフォームにおける建築確認申請の流れを解説します。
ここでは、リフォームにおける建築確認申請の流れを解説します。
1. 確認申請の必要性を確認
まず、計画中のリフォームが建築確認申請の対象かを確認します。リフォームの内容によっては、建築確認が不要な場合もありますが、増築や大規模な修繕の場合、確認申請が必要となるケースが多いでしょう。
2. 申請書類の準備
申請が必要と判断された場合、次に書類の準備に進みます。以下の申請書類が一般的に必要です:
・確認申請書
・設計図書(付近見取り図、配置図、平面図、立面図、断面図、求積図)
・構造計算書(必要な場合のみ)
・各種計算書(シックハウス計算、採光計算など)
・既存建物の確認申請書類・検査済証
・建築計画概要書
・その他地域や工事内容に応じた必要書類
これらの書類は、リフォーム会社が準備を代行し、行政機関の要件に従って整えるのが一般的です。
・確認申請書
・設計図書(付近見取り図、配置図、平面図、立面図、断面図、求積図)
・構造計算書(必要な場合のみ)
・各種計算書(シックハウス計算、採光計算など)
・既存建物の確認申請書類・検査済証
・建築計画概要書
・その他地域や工事内容に応じた必要書類
これらの書類は、リフォーム会社が準備を代行し、行政機関の要件に従って整えるのが一般的です。
3. 申請手続き
書類が整ったら、行政機関または指定確認検査機関へ申請を行い、法的基準に適合しているかの審査を受けます。
この審査には通常2週間から1か月程度かかり、審査の結果、設計図などに修正が求められることもあります。その場合は指摘事項に基づき、再度設計や書類の調整が必要です。
審査に通れば、リフォーム工事に着手できる「確認済証」が発行されます。確認済証が出るまで工事は始められないため、申請手続きには十分な時間を確保しておくことが大切です。
この審査には通常2週間から1か月程度かかり、審査の結果、設計図などに修正が求められることもあります。その場合は指摘事項に基づき、再度設計や書類の調整が必要です。
審査に通れば、リフォーム工事に着手できる「確認済証」が発行されます。確認済証が出るまで工事は始められないため、申請手続きには十分な時間を確保しておくことが大切です。
4. 中間検査と完了検査
確認済証の発行後、リフォーム工事の進行中に「中間検査」、工事終了時に「完了検査」が必要になる場合があります。
完了検査は、建物全体が法的基準に適合しているか最終的に確認するもので、問題がなければ「検査済証」が発行されます。これにより、法的にも安全性が認められた建物として、正式に使用が許可されます。
完了検査は、建物全体が法的基準に適合しているか最終的に確認するもので、問題がなければ「検査済証」が発行されます。これにより、法的にも安全性が認められた建物として、正式に使用が許可されます。
建築確認申請にかかる費用

建築確認申請にかかる費用の内訳は以下のとおりです。
・確認申請手数料
・中間検査手数料
・完了検査手数料
・書類作成、申請代行費用
建物の構造や規模、工事内容、地域によって変動しますが、一般的には総額で15万円~20万円が相場となります。
さらに、2025年以降の法改正で構造計算や省エネ基準の提出が追加される新2号建築物に分類される建物では、申請に必要な書類や検査項目が増えるため、従来よりも高額になる可能性があります。
事前にリフォーム会社に費用についても確認しておきましょう。
・確認申請手数料
・中間検査手数料
・完了検査手数料
・書類作成、申請代行費用
建物の構造や規模、工事内容、地域によって変動しますが、一般的には総額で15万円~20万円が相場となります。
さらに、2025年以降の法改正で構造計算や省エネ基準の提出が追加される新2号建築物に分類される建物では、申請に必要な書類や検査項目が増えるため、従来よりも高額になる可能性があります。
事前にリフォーム会社に費用についても確認しておきましょう。
まとめ
建築確認申請は、安全な建物づくりに欠かせない手続きであり、新築や増築はもちろん、工事内容によってはリフォームでも必要になります。
2025年の法改正により、とくに小規模住宅でも申請対象となるケースが増える見込みです。リフォーム計画を立てる際には、建築確認申請が必要かどうかを早い段階で確認し、申請が必要な場合はリフォーム会社と十分に相談して手続きを進めましょう。
また、法改正後は構造計算や省エネ基準の提出が追加されることで、従来よりもコストが増える可能性もあります。そのため、費用についての見積もりや手続きのスケジュール管理も重要です。安全で快適な住まいへとリフォームするためには、改正内容を踏まえた計画をしっかりと立てていきましょう。
静岡県西部・浜松のリフォーム・リノベーションなら、信頼と実績で選ばれる遠鉄のリフォームへ。
戸建・マンションのキッチン・ユニットバス・トイレ・洗面など、住まいのあらゆるお悩みに確かな技術と魅力的なプランでお応えします。
■リフォーム施工事例を見る
https://www.entetsureform.com/works/
■お客様の声を見る
https://www.entetsureform.com/voice/
2025年の法改正により、とくに小規模住宅でも申請対象となるケースが増える見込みです。リフォーム計画を立てる際には、建築確認申請が必要かどうかを早い段階で確認し、申請が必要な場合はリフォーム会社と十分に相談して手続きを進めましょう。
また、法改正後は構造計算や省エネ基準の提出が追加されることで、従来よりもコストが増える可能性もあります。そのため、費用についての見積もりや手続きのスケジュール管理も重要です。安全で快適な住まいへとリフォームするためには、改正内容を踏まえた計画をしっかりと立てていきましょう。
静岡県西部・浜松のリフォーム・リノベーションなら、信頼と実績で選ばれる遠鉄のリフォームへ。
戸建・マンションのキッチン・ユニットバス・トイレ・洗面など、住まいのあらゆるお悩みに確かな技術と魅力的なプランでお応えします。
■リフォーム施工事例を見る
https://www.entetsureform.com/works/
■お客様の声を見る
https://www.entetsureform.com/voice/